他学会・講演会等の開催情報
このページに学会・講演会等の情報の掲載を希望される場合には、以下の連絡先まで、リンク先やその他の必要な情報をお寄せください。もし可能でしたら、こちらのテンプレートの通りにお願いいたします(作成が難しい場合は通常のフォーマットのもので構いません)。なお、エイチティーティーピーから始まるリンクに関しては、安全ではないと判定される可能性が高いため、エイチティーティーピーを★に置き換えて掲載させていただきます。また、会員メーリングリストによる周知をご希望の場合はあわせてお知らせください。その場合、メーリングリストで周知する文面をメールタイトルも含め、別ファイルでご用意ください。
連絡先: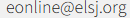 [お手数ですが、手入力をお願いいたします。]
[お手数ですが、手入力をお願いいたします。]
※送信後、休日を除き72時間以内に掲載されない場合には、事務局に届いていない可能性があります。再送信いただくか、事務局にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
学会・シンポジウム・講演会
日本ホプキンズ協会例会
[日時] 2026年3月29日(日)13:30~17:00
(Zoomによるオンライン開催)
【概要】ジェラード・マンリー・ホプキンズの詩の試訳と解説を担当者が行い、そのあと、その発表内容について詳細に検討します。テキストはW. H. Gardner and N. H. Mackenzie, eds., The Poems of Gerard Manley Hopkins, 4th ed., Oxford Univ. Pressを使用します。
【参加方法】参加ご希望の方は、お名前とご所属をお示しの上、3月24日(火)までに下記問い合わせ先までにご連絡ください。
【プログラム】
13:30~17:00 (途中20分の休憩)
Rosa Mystica(27)stanza 4
担当 高橋 美帆
Rosa Mystica (27) stanzas 5-8
担当 山田 泰広
【問い合わせ先】日本ホプキンズ協会事務局 高橋 美帆
miho☆kansai-u.ac.jp[お手数ですが、☆をアットマークに変更の上、手入力をお願いします]
詳細は学会のHPをご覧ください。
大学英語教育学会(JACET) 第1回 JAAL in JACET学術交流集会(夏季、2026)発表応募について
【日程】2026年8月27日(木)
【場所】立命館大学 大阪・いばらきキャンパス
【概要】AILA (International Association of Applied Linguistics) は、応用言語学研究の発展と研究者の交流を促進する学会として、1964年に設立されました。応用言語学会は一国に一つ組織されており、日本ではJACETの中に、The Japan Association for Applied Linguistics (JAAL) in JACET が 1984年に設立されています。
この度、第 1 回 JAAL in JACET 学術交流集会(夏季、2026)を、第65回JACET国際大会(大阪、2026)の2日目に同時に開催することとなりました。下記要領で応用言語学に関する研究発表(口頭発表のみ)を募集いたします。本学術交流集会は、JACET会員並びに提携学会等の会員以外の方も筆頭者として発表することが可能です。
発表者による Proceedings(査読無し)も発行されますので、皆様ふるってご応募ください。
【応募期間】2026年2月6日(金)〜2026年3月6日(金) 23:59(JST)
【応募方法】
(1)応募内容
英語の発表タイトルと要旨(300 語以内)を提出してください。
次の 3 つの観点を考慮して審査します。
・ 内容(研究目的、研究方法、分析結果等)
・ 論理的構成(研究目的、内容、結論の一貫性)
・ 研究意義(応用言語学、外国語教育、関連諸科学分野の改善と発展への示唆)
※ 一度提出された発表タイトルと要旨は差し替えや訂正はできません。
※ 発表要旨には図や表、特殊文字、文献リストは入れないでください。
(2) 応募手順
JACET ウェブサイト から、「Convention≫ 2026 ≫ JAAL in JACET Call for Papers」に進み、Abstract Submissionから応募してください。共同発表は第一発表者のみが入力してください。
【問い合わせ先】
一般社団法人 大学英語教育学会事務局
TEL: 03-3268-9686(平日 13 時~16 時)
E-mail: jacet☆zb3.so-net.ne.jp(☆をアットマークに)
中央大学人文科学研究所「英国モダニズム文学・文化史研究」チーム 公開研究会(責任者:福西 由実子)
【日時】2026年3月26日(木) 16:15~18:45
【開催場所】中央大学 茗荷谷キャンパス 5階 5N02教室
https://www.chuo-u.ac.jp/uploads/2025/09/access_myogadani_01.pdf?1771466266633
【報告者①】秦 邦生 氏(東京大学准教授)
【テーマ】ヒッチコック、コンラッド、モダニズム、そして「共感/エンパシー」の問題
【要 旨】例えば2021年に刊行されたブレイディみかこの『他者の靴を履く』など、近年日本でも「共感/エンパシー」をめぐる言説が広く注目を集めている。遡れば、ドイツ語 Einfühlung の訳語として empathy が英語圏の心理学に導入されたのは20世紀初頭であり、英文学研究においても “sympathetic realism” から “empathic modernism” への転換が論じられてきた。本発表ではこの感情史的枠組みを踏まえ、1936年にアルフレッド・ヒッチコックが Sabotage として映画化したジョゼフ・コンラッド『密偵』(1907年)を主な題材として、「共感」の情動的ダイナミズムに介入・操作する小説と映画のモダニズム的技法とその変遷を検討する。
【報告者②】中村 亨 研究員(中央大学教授)
【テーマ】マシン・エイジへの抵抗―ヘミングウェイとヴォーティシズム
【要 旨】機能に徹した機械をモデルに新たな文化を生み出そうとする20世紀初頭の思潮と、アーネスト・ヘミングウェイの文学との関係を、前衛的芸術運動ヴォーティシズムとの接点を軸に検討する。彼の簡潔で抑制された文体は、機械を創造物の模範と見なす時代精神と通底する一方で、効率化と規格化に傾倒する社会に対する彼の屈折した姿勢をも映し出しているのではないか。本報告では、彼の著作および運動の中心人物であったエズラ・パウンド、ウィンダム・ルイスらとの関係について考察する。
【参加方法】
・研究会参加の事前申し込みは不要です。
・研究会後の懇親会(茗荷谷駅周辺、19:00-21:00の予定)にご参加希望の場合は、3月19日(木)までに、担当者(福西:yumi29.24h@g.chuo-u.ac.jp)までご連絡ください。
・同日14:00-16:00に、中央大学人文科学研究所「ジェンダー/セクシュアリティと表象文化」チームによる公開研究会も開催されます。両研究会の「はしご参加」も大歓迎です。ぜひご参加ください。(詳細:https://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/culturalscience/event/2026/02/84453/
東大英文学会および後藤和彦先生最終講義
【日時】2026年 3月14日(土)15:00-17:30
【場所】東京大学本郷キャンパス 法文2号館1番大教室
【概要】
古屋耕平「文系とAI——アメリカ文学の場合」
後藤和彦(最終講義)「Mark Twainと夏目漱石——追憶と諧謔」
【参加方法】参加自由・無料
【懇親会】
同日 18:00-20:00
会場:カポ・ペリカーノ
会費:10,000円(学生5,000円)程度の予定
登録フォーム: 東大英文学会総会 2025-26 - Google Forms
ご回答期限: 2026年3月1日(日)
【お問い合わせ先】eng☆l.u-tokyo.ac.jp(☆をアットマークに)
日本国際教養学会(JAILA)第14回全国大会
【日時】2026年3月14日(土) 9:15~ ※ 受付開始は8:45
【場所】宮城教育大学[2号館3階]仙台市青葉区荒巻字青葉149
【概要】
日本国際教養学会(JAILA)は、研究分野の細分化と専門化が果てしなく続く現在の研究および学会活動の潮流の中で、真に必要とされる知識と教養を国際的な視野に立って共有することを目的とし、哲学、歴史、社会科学、自然科学、芸術、教育、外国語、環境など多方面にわたる研究活動を行っております。全国大会も14回目を迎えました。
大会の詳細につきましては、JAILAホームページをご覧ください。「大会案内ページへのリンク」から、口頭発表プログラムと発表概要集(現在準備中)、その他詳細のご案内をご覧いただけます。
ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。
【参加方法】
対面形式(ポスター発表、特別講演はオンライン参加可)
参加申込フォームで受け付けております。
対面参加、オンライン参加ともに事前のお申込みが必要です。
[申込締切]3月4日(水)正午
【プログラム】
詳細はJAILAホームページ上の「大会案内ページへのリンク」へ。
以下、特別講演のご案内です。
15:20〜16:50
【司会】Dr. Nami Sakamoto Doshisha University
【講師】Dr. Sender Dovchin Curtin University
【演題】First Languaging and First Knowledging and the Future of Indigenous Education: Perspectives from Australia, Mongolia, and Japan
【内容】
First Nations peoples have sustained their cultural and linguistic practices for tens of thousands of years, developing sophisticated First knowledge of nature, land, water, sky, seasons, astronomy and navigation since the earliest moments of human existence. Although they may not have relied on modern technological instruments, they have long possessed intricate knowledge systems that continue to sustain their languages, cultures, communities, and ecosystems across generations. This profound practice of First Knowledging also brings forth an awareness of First Languaging - the living and evolving expressions of First Languages that have existed since the dawn of humanity. Humans have always been languaging; yet First Nations peoples have preserved a unique clarity and connection to this essence. For them, language is not merely a means of communication but an interwoven tapestry of spiritual expression, storytelling, and embodied systems of First Knowledges that nurture both cultural and ecological worlds.
This lecture explores the intersections of First Knowledging and First Languaging among Indigenous communities in Australia and Mongolia, illuminating how linguistic and cultural continuity shape identity, learning, and belonging. By examining the dynamic interplay between Indigenous and dominant languages across homes, schools, and communities, it identifies pathways for embedding these epistemologies in curriculum design and classroom practice. Extending to Indigenous contexts in Japan, the lecture considers how First Languaging and First Knowledging can inform transformative, inclusive, and culturally responsive approaches to Indigenous education for the future.
Lecturer Profiles:
Professor Sender Dovchin is Dean International, Faculty of Humanities, and Senior Principal Research Fellow at the School of Education, Curtin University, Australia. She is an internationally recognized scholar in applied linguistics, known for her research on translanguaging, migrant and Indigenous education, and language ideologies and identities. She has been named a Top Researcher in Language & Linguistics by The Australian Research Magazine (2021, 2024) and listed among the world’s top 2% most-cited linguists (Stanford University list).
【お問い合わせ先】
JAILA大会運営委 jaila.annualmeeting☆gmail.com(☆をアットマークに)
日本シェリー研究センター第34回大会
【日時】2026年3月14日(土)12時30分受付開始
【場所】帝京大学 霞ヶ関キャンパス(平河町森タワービル9階)
【参加方法】ハイフレックス形式 (対面+オンライン)
【プログラム】
1. 12:40 開会の辞 会長 木谷 厳
2. 12:45~13:15 研究発表
【司会】笠原 順路
【講師】菅谷 菜々美
【演題】ワーズワスの“The Brothers”における「墓碑銘」の両義性
3. 13:30~15:30 シンポージアム
【演題】19世紀後半におけるシェリー受容とヴィクトリア朝の詩学(1850–1890)
【司会/コーディネーター】木谷 厳
【講師】松村 伸一
【演題】「長いロマン主義」の連続と断絶――韻律、フィロロジー、二重詩
【講師】木谷 厳
【演題】ヴィクトリア朝後期におけるシェリーのカノン化にJ. A.シモンズが果たした役割
【講師】関 良子
【演題】19世紀後期のシェリー読み直し、あるいは読みかえ――Poetics & Politics
4. 15:45~16:45 特別講演
【司会】池田 景子
【講師】阿部 美春
【演題】メアリ・シェリーの死後肖像は何を語っているのか
5. 16:50 年次総会 昨年度分会計報告・役員改選・その他
詳細は日本シェリー研究センターHPに掲載の大会プログラムをご覧ください。
【お問い合わせ先】日本シェリー研究センター事務局 池田 景子
keiko.ikeda☆setsunan.ac.jp (☆をアットマークに変更)